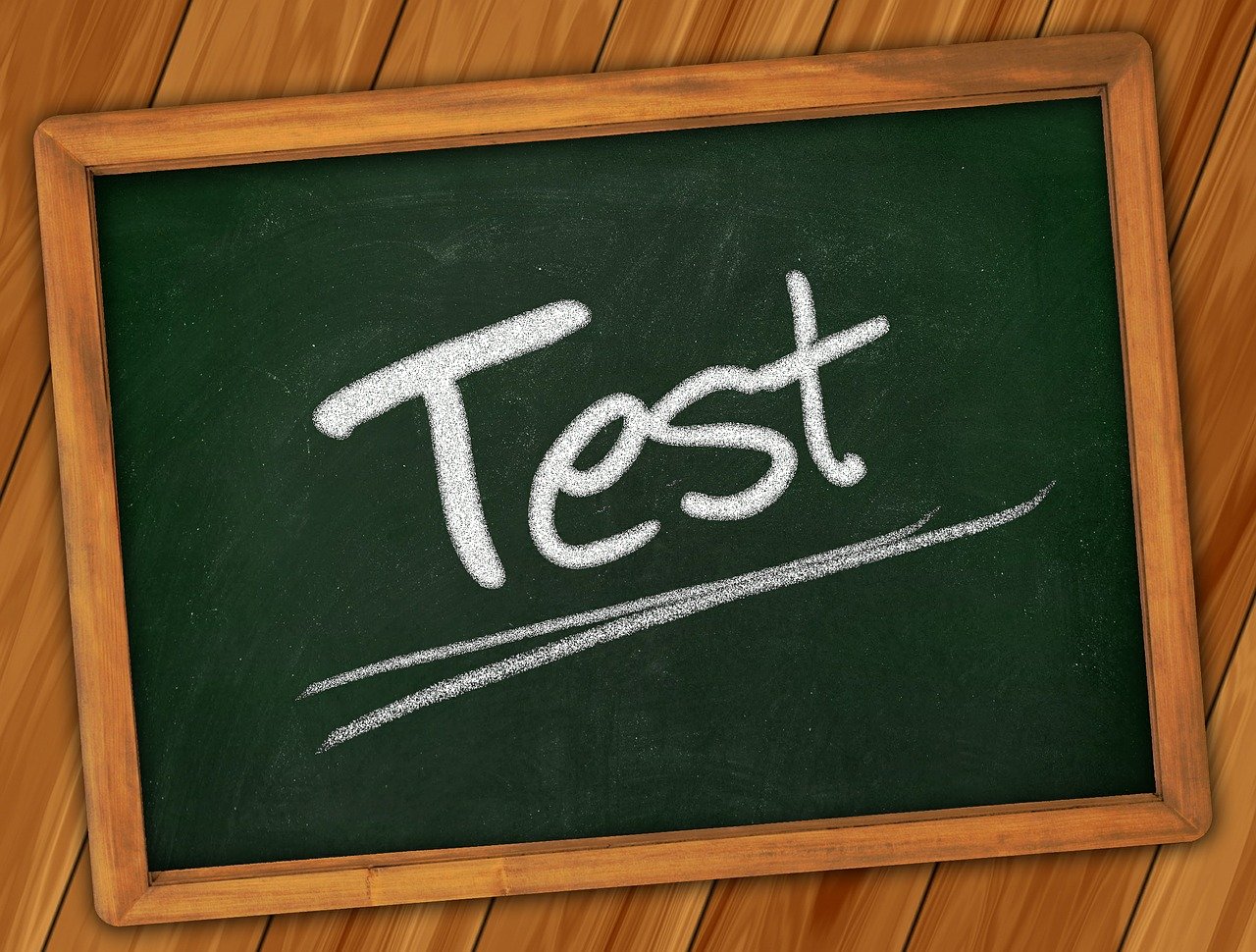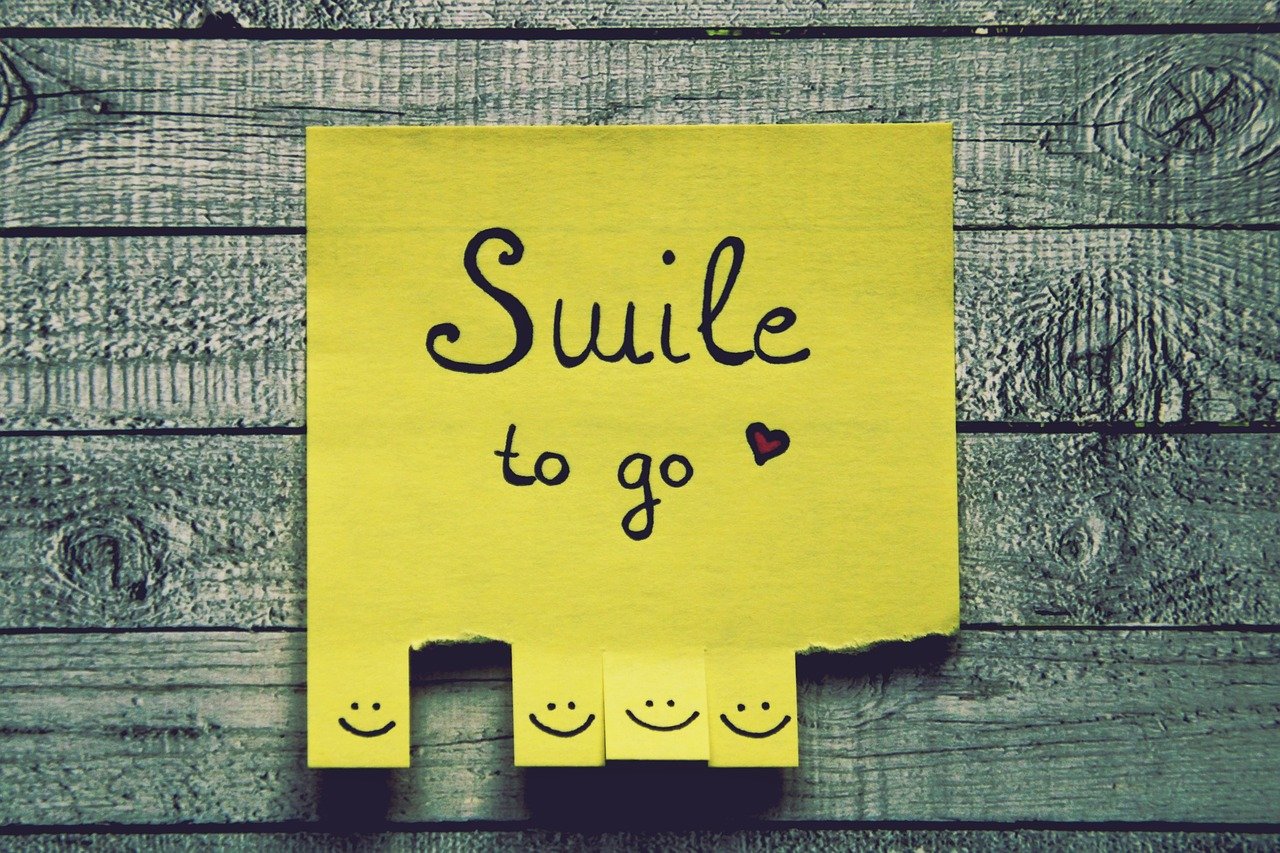前回、日常の「お手伝い」ではなく、子どもが「得意なこと」をサービスとして提供し、その対価として報酬(お小遣い)を受け取る。という方式の「報酬制」をオススメしました。

今回は、このいわば「お助けマン報酬制度」を導入することによって、どのようなメリットがあるかについて考えてみましょう。
メリット1:世間のニーズを読みとる力がつく
提供可能なサービスを書き出すときに注意することとして、「親が苦手なことやいつも困っていること×自分が得意なこと」を軸に、提供できるサービスを考えること。と、申し上げました。
「報酬制」ですので、まずはサービスを受けてもらわないと話になりません。だから、よりたくさんのサービス依頼が集まるように
どんなことを引き受けてあげたら喜ぶのだろう?
お父さんは何が苦手だっけ?お母さんは何にいつも困っていたっけ??
注意深く観察し、思い出し、考えを巡らし、ニーズのあるサービスを一生懸命考えるはずです。観察眼を鍛え、市場のニーズを読み取る力をもつことは、将来かならず役に立ちます。仕事でも、株式投資でも、人間関係でも!観察眼とニーズを読みとる力をもっていれば、より有利に自分の人生を進められる可能性が高まることでしょう。
メリット2:自分の得意なことに敏感になる
これも重要なことです。ポートフォリオワーカーのすすめについても記事にしましたが、得意なことを増やすことは、将来の収入の柱を増やすチャンスにつながります。いまのうちから
- 自分の得意なことをしっかり考え、見つけ出すこと
- 報酬(お小遣い)を増やすために得意なこと(提供できるサービス)を増やすこと
これらのことを考える習慣がつけば、年々得意なことは確実に増えていきます。年齢が上がるにつれ思考の幅も広がっていきますから、あれもこれもできるかも!と、提供可能なサービスリストはどんどん増えていくでしょう。興味のあることや趣味、得意なことをできるだけたくさん増やしていって、将来の可能性も広げていってほしいと思います。

メリット3:社会のしくみを知ることができる
他人がほしがるサービスや能力を提供したことに対し、「ありがとう」という意味を込めて報酬が支払われる。そうやって、毎日たくさんのお金が動いて社会は成り立っている。そんな社会のしくみを、どんなに丁寧に説明するよりも分かりやすく、理解することができることでしょう。
このとき、、サービスの対価として報酬額を設定する以上は、相手が「ありがとう」という想いを込めて報酬を支払うことができるよう、責任を持って丁寧に、相手が満足するレベルでサービスを提供しなければいけない。ということも合わせて教えてあげたいですね。
メリット4:需給のバランスについて学ぶことができる
報酬額をきめるとき、子ども自身に自由に決めさせると異常に高かったり、その逆でものすごく安かったり・・・笑っちゃうような価格設定をしてくることもあります。でも、親だってお金を払うのですから、あまりに高かったら頼まずに自分で頑張ろうかな。と思いますよね。それでいいと思うのです。
いいサービスでも、価格と見合っていなければ依頼は来ない(需要はない)
あまりに安かったら、依頼がたくさん来て大忙しなのにお小遣いは増えていかない
気づかせてあげるきっかけ作りやある程度の誘導は必要ですが、自分で価格設定をするからこそ見えてくる世の中にある「値段」は、需要と供給のバランスで決まっている。ということを学ぶことは、とても意味のあることだと考えます。
おわりに
お小遣いにおける報酬制を否定する記事をよく見かけますが、採り入れ方によっては驚くほど有意義で面白みのある、いい制度であると思っていただけたかと思います。我が家でも実際に、娘たちには「お助けウーマンリスト」として、提供できるサービスとその価格を一覧にしてもらっています。これがまた、なかなかうまいところをついているサービスが揃っているので、結果として大いに活用しています。これは、子どもの年齢を問わずできることだと思うので、大きくなるまでリストを更新しながら続けていく予定です。大きくなった息子(娘)のリストに「疲れて帰ってくるときに車で駅まで迎えに行く(ただし雨の日は無料)」なんて見つけたらにやけちゃいませんか?!