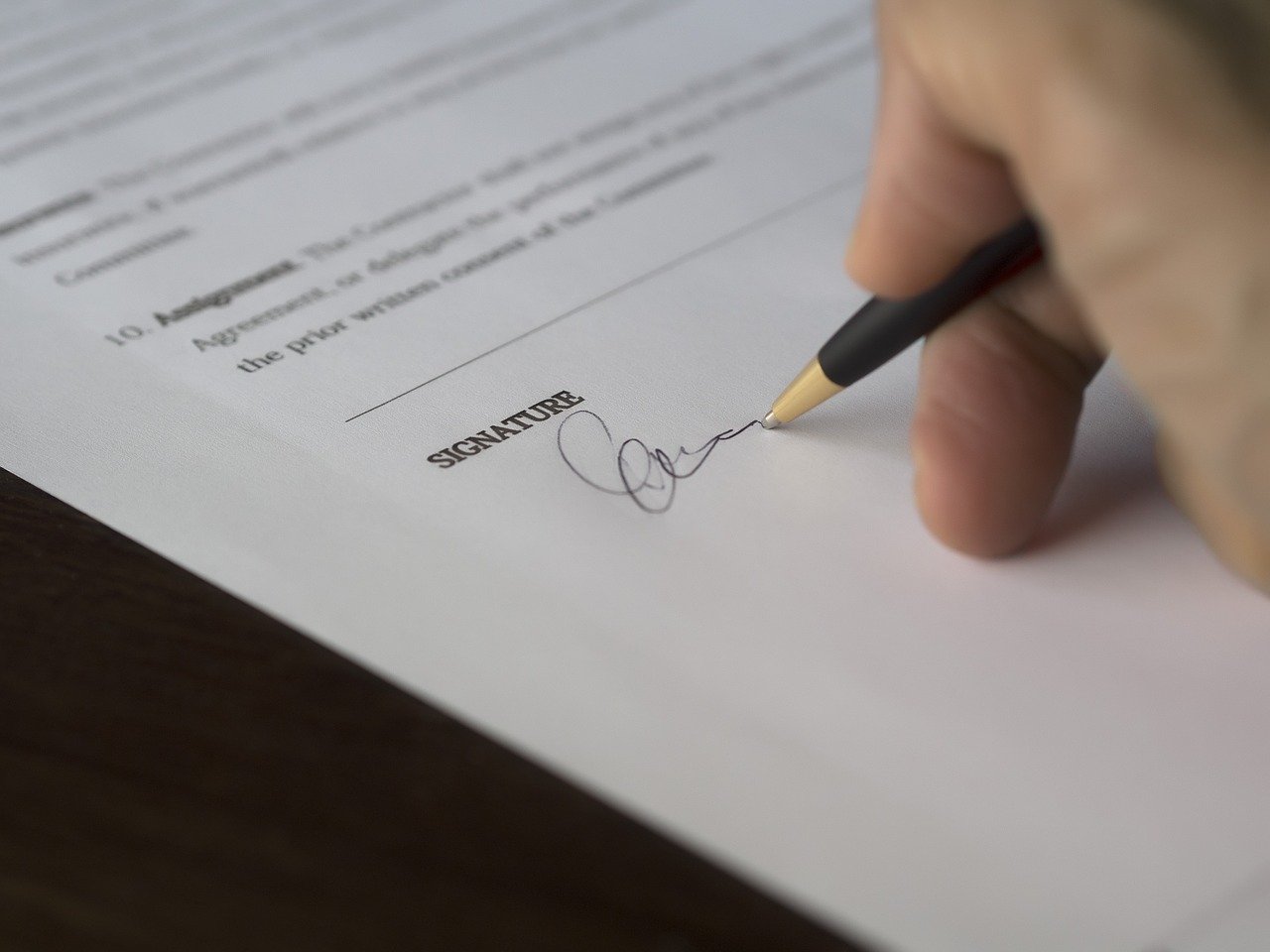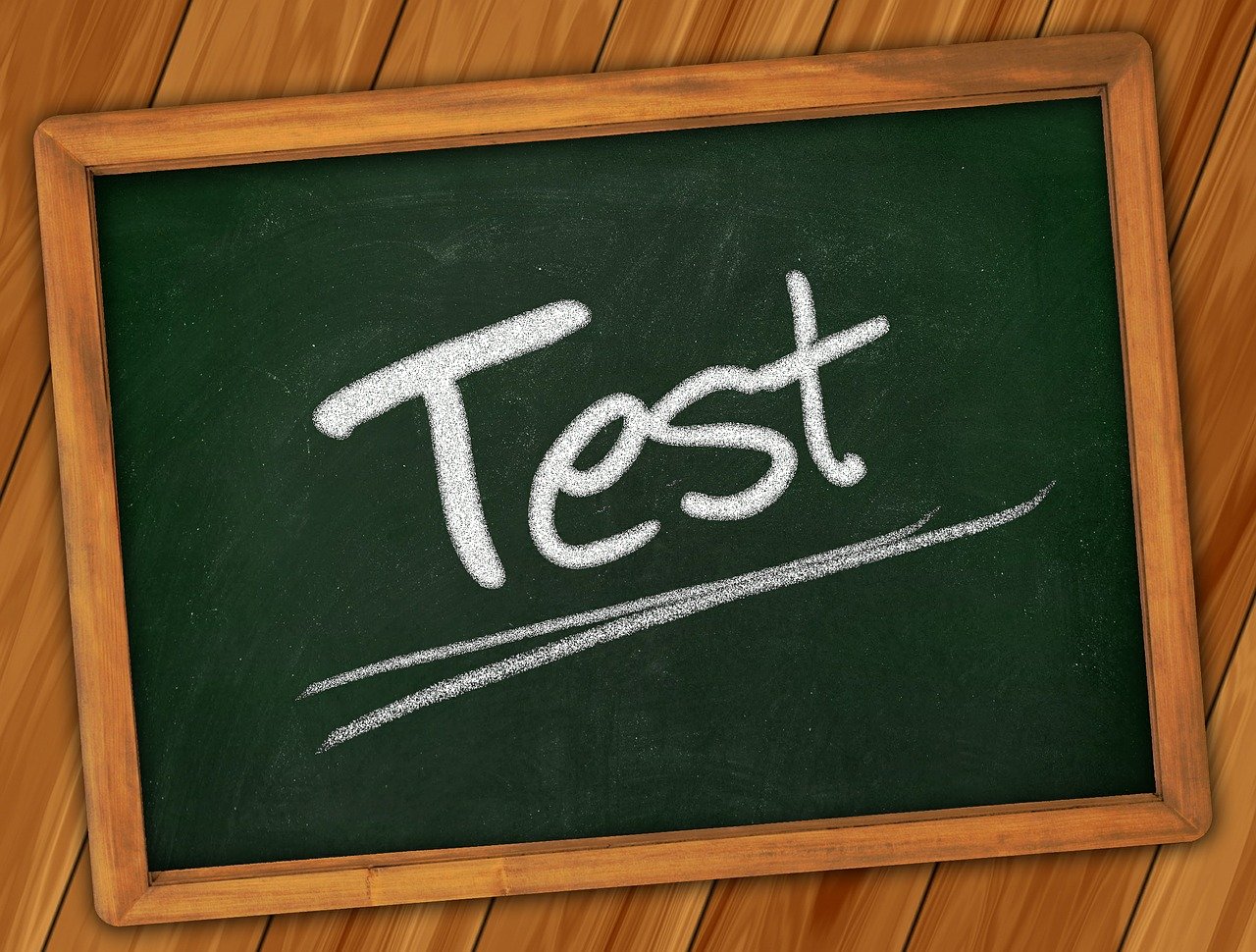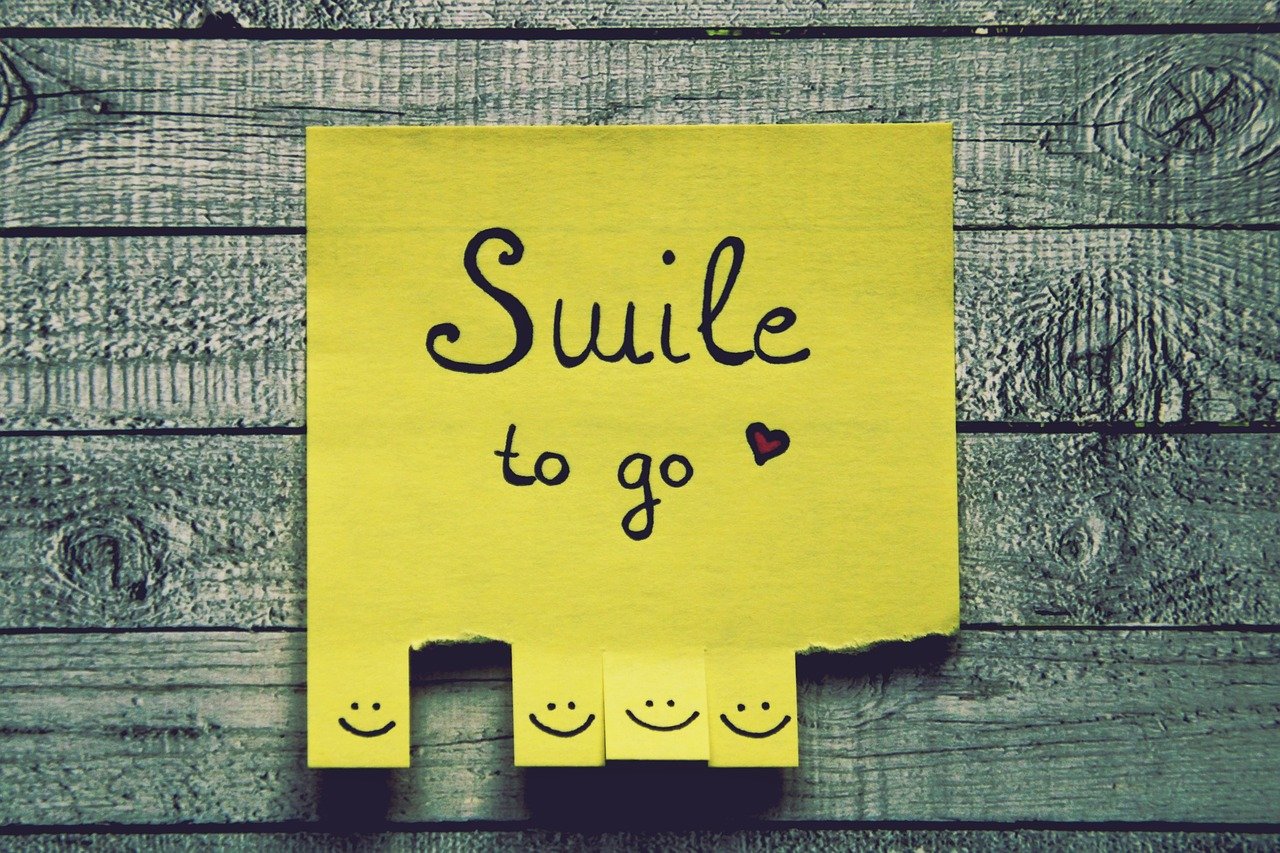以前、身近なお小遣いを用いて子どもと契約書を交わし、将来に向けて実用的文章に触れておくことをおすすめしました。そしてその中で、大まかな作成ポイントはご紹介しましたが、今回はより詳しく「お小遣い契約書」に盛り込むべき記載事項をひとつひとつご紹介していきます。
契約書に慣れることは自分を守ることに繋がる!こちらの記事もCheck!

契約書作成時の大まかなポイントはこちらの記事でCheck!

お小遣い契約書に盛り込むべき事項
ではさっそくお小遣い契約書に盛り込むべき事項を、我が家の契約書(お小遣い約束書)を参考例として挙げながら確認していきましょう。
※グレー色「参考」の枠内の文言は、実際に我が家で使用しているお小遣い約束書の文言です。甲は親、乙が子どもになります。
※「項」と出てきたら、1.2.3.4.といった数字のあとに続く文章、「号」と出てきたら①②③④といった数字のあとに続く文章を指しています。
①「大前提のあたり前」を盛り込もう!
第1条(はじめに)
1.甲が乙に渡すお小遣いは、甲が働いて得た賃金が原資となっていることを忘れず、大切に使用して下さい。
2.乙はお小遣いをもらうにあたり、積極的にお手伝いを行うなど、○○家の一員として家庭に貢献するよう努めて下さい。
お小遣いは大抵の場合、親が働いて得たお金の中から出しています。至極当たり前のことですね。しかし、その当たり前をきちんと伝えたことはありますか?子どもたちはきちんと理解していますか?この当たり前の事実を子どもが理解しているかしていないかは、お金に対する価値観を育てる上で大切なことだと思っています。
お小遣いは毎月続いていきますから、そのうち子どもにとって「もらえて当たり前のもの」に変わっていきます。その当たり前が続くのはなぜなのかということに少し想いを馳せ、「感謝して受け取る」「大切に使う」ということをそれこそ当たり前にできる子であってほしいと思います。
そういった普段あえて口にして伝えてはいない願いや想いを自然な形で伝えられるのも、文書化する利点のひとつではないでしょうか。
②「お小遣いを通して学んでほしい目的」を盛り込もう!
第2条(狙い)
1.甲は、このお小遣いの渡し方を通して、「複利の仕組みを学ぶこと」「投資・消費・浪費の区別をつけること」ならびに「効率的な投資で最大限のリターンを得る方法について考えること」を乙に期待しています。
2.「○○円以上貯まった分は預金口座に移す」「人のために使うお金は別に管理する」「毎月○○円は貯金にまわす」「欲しいもの貯金をして貯まったら気持ちよく使う」など、お小遣いの使い方や貯め方について自分なりのルールを作り、お金を上手に管理できるようになっていって下さい。
マネー教育をかねてお小遣いを渡している場合には、「お小遣い」から何を学んでほしいと思っているのかをハッキリと伝えましょう。もちろん、狙いとするひとつひとつの事柄については丁寧に教えてあげてください。その上で、それらをお小遣いを通じて継続的に学んでいってほしいということを明記し、意識させ、成長を促していきます。
複利を学ぶならお小遣いは定率制が最適!こちらの記事でCheck!

お小遣いから投資をおこなうと学力UPにも繋がる!こちらの記事でCheck!

③「お小遣いの基本ルール」を盛り込もう!
第3条(月々のお小遣いの金額)
1.月々のお小遣いの金額は、各月末日時点での残高に、甲が定めた通常月の利率を乗じた金額とします。
2.前項の利率はお小遣い残高、甲の懐事情、乙のお小遣いの使い道等を勘案し、毎年3月中に決定し、原則として当年4月分~翌年3月分まで適用します。
3.1項にかかわらず、乙が各月1日から末日までの1ヶ月間に「投資」として使用した金額が、甲が定める一定の金額以上であった場合には、翌月のお小遣いは、別途定めた1項よりも有利な利率を乗じて得た金額とします。
4.1項および3項の利率、その他詳細ルールについては別紙にて説明します。
第4条(お小遣いの渡し方)
1.乙は、毎月月末日以降に「お小遣い帳」「現金残高」ならびに「通帳残高」を甲に提示し、翌月のお小遣いの計算基礎となる金額の確認を受けて下さい。
2.前項の確認は、毎月15日までには行うこととし、15日までに乙からの提示がなかった場合にはその月のお小遣いはなしとします。
3.甲は、1項の確認を行った際は、速やかにお小遣いの額を計算し、その翌日から起算して3営業日以内に乙にお小遣いを渡します。
4.甲は、3項に規定した日を過ぎてもお小遣いを渡せない場合は、1日につき当月のお小遣い額の10%の遅延金を加算して渡します。
契約書ですから、お小遣いの額や渡す日などの基本ルールはもちろん盛り込みます。口頭であらかじめ決めていたことを文章に落とし込むだけですね。ただ、ここで是非おすすめしたいのが参考の第4条3項、4項で述べているような親側が守るべきルールを盛り込むこと。
契約書は一方的なものではなく、守るべきことについて両者が合意した内容を盛り込み確認し合うためのものです。親側は権利だけを主張し、なにも守るべき義務を負わない。では契約書としても成り立ちませんし、何より子どもの心に響きません。起こりそうな事態を予測して、親側もルールを守る義務があること。守れなかったときには子ども側の権利を守るため罰則を受けること。その意思を示しましょう。そうすることで両者がともにルールに則り約束事を守っていくものだという契約書の意義を教えることができます。
④「お小遣いの使用範囲」を盛り込もう!
第5条(お小遣いの使用)
1.乙は、以下のものを除き、嗜好品、学用品問わず日常生活において「購入したい」と思うものは原則として全てお小遣いの中から捻出するものとします。
① 学費、月謝、定期代
② 学校または習い事先から直接請求のくるもの
③ 学校または習い事で使用する高額な必要品であって甲が購入を認めたもの
④ 交通費
⑤ 美容院代
⑥ 服飾品代
⑦ 携帯利用料金
⑧ 映画、美術館等およびコンサートのチケット代
⑨ 家庭内で一括して購入する消耗品等
⑩ その他甲が購入を申し出たもの
2.お小遣いの使用先は、原則として乙が自由に決めて構いません。ただし、お金は便利なものである反面、トラブルの原因になりやすいものです。自分自身と周囲の大切な人を守るために次の各号に定める行為についてはしないで下さい。
① 友人間でのお金の貸し借り
② インターネット上での物品等の購入
③ 月々のお小遣い額を超える金額の物品等の購入
④ その他、乙が使用に際し少しでも不安を抱く行為
3.やむを得ない事情により、前項各号に定める行為を行おうとする場合には、必ず事前に甲に相談して下さい。事後報告は一切認めません。
4.前項にかかわらず、2項3号に規定する物品であって、明らかに投資に分類されるものについては、自由に購入して構いません。なお、投資か否かについては第6条を参考にし、判断して下さい。
お小遣いの使用範囲については揉めやすい部分なので、忘れずに明記しましょう。参考のように列挙するのもいいですが、結構細かく挙げるとキリがないので、もっとザックリと作成するのでもいいと思います。いずれにしても契約書的には、1項10号のような形で例外規定を作っておくと融通が効きます。
また、2項の規定のように使用してはいけないものの範囲を記載するのもおすすめです。我が家では友人間のお金の貸し借りなどが心配だったので、お金はトラブルになりやすいものであるということを伝えるためにこの規定を作成しました。
長くなりましたので、その2に続きます・・・。