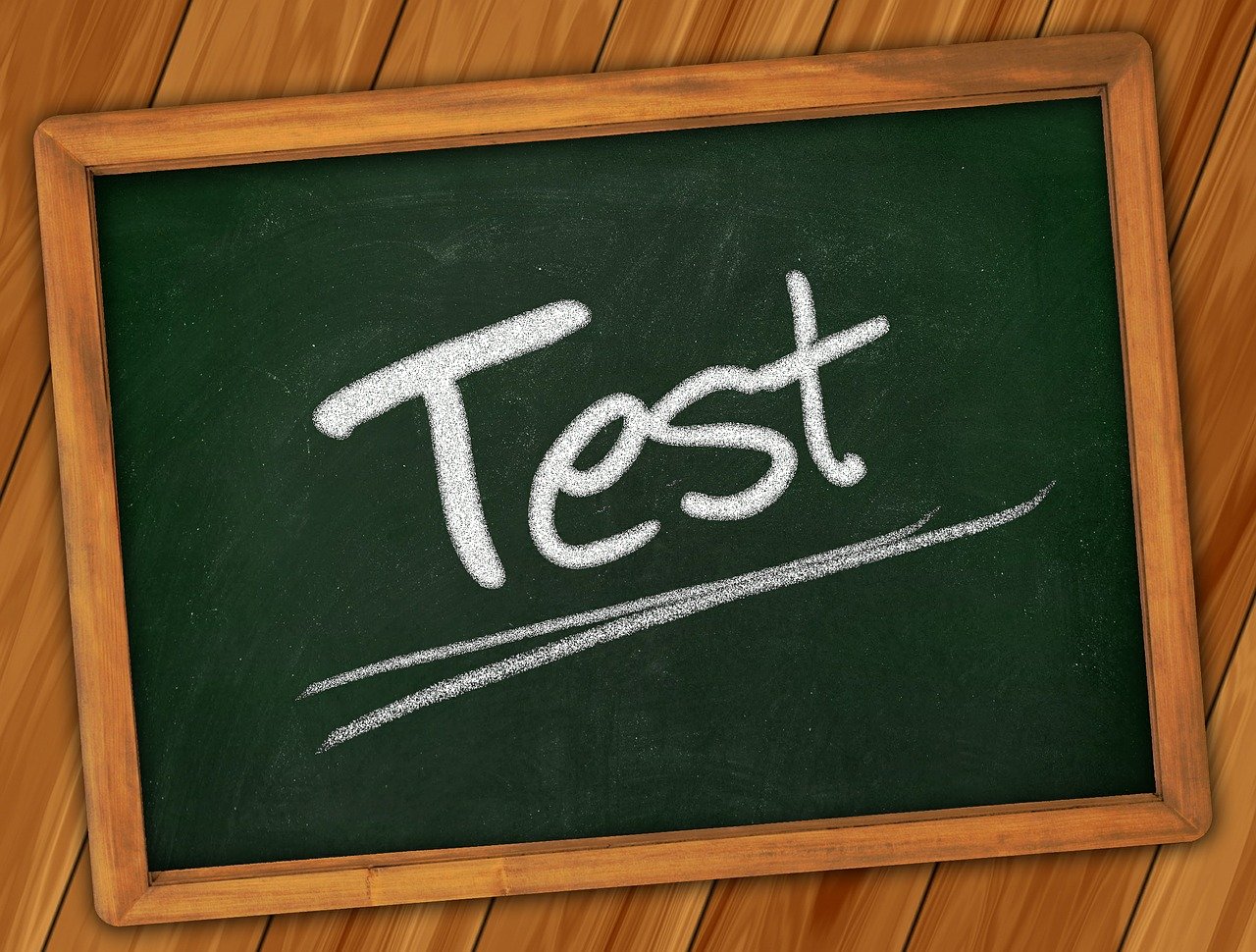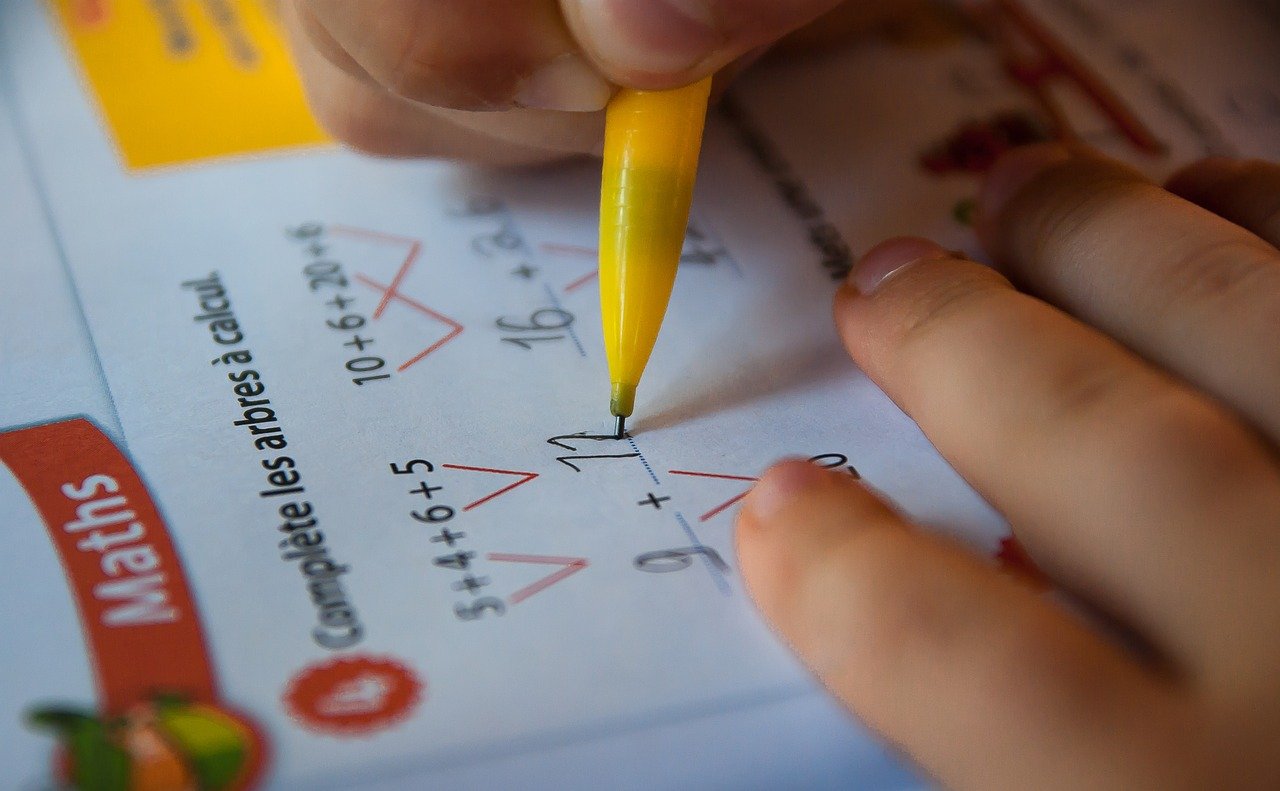自主学習おすすめのネタを紹介します
現在多くの小学校で取り入れられている自主学習の宿題。「毎日1ページ取り組むこと」などとされていて、何をすればいいかもはやネタ切れ!と、頭を悩ませているご家庭もあるのではないでしょうか?娘ふたりの自主学習、ともにネタを探し続けた日々を振り返り、おすすめの取り組みをご紹介します。
1.四字熟語
4つの漢字に大きなメッセージが込められた四字熟語。成り立ちや意味を調べてみるとそれぞれにストーリーがあって感動することすらあります。作文なんかで四字熟語が使えるとカッコイイし、書き初めでも役に立ちますよ。「数字を使った四字熟語」や「同じ漢字を繰り返す四字熟語」など、的を絞った学習もいいですね。
2.ことわざ
生活の中で生まれた古くからの言い伝えを短い言葉にぎゅっと閉じ込めたことわざ。現代でも「なるほど、そのとおり!」と思うものばかりで知れば知るほどどんどん楽しくなっていきます。
3.慣用句
こちらも国語の王道。日常生活の中で使われることも多い慣用句は、意味を知っていないと発言者の意図が分からずトンチンカンな対応をとってしまうことになりかねません。何気なく使っている言葉も実は慣用句だった、なんていう驚きもあります。慣用句は語彙としてたくさん増やしておくといいですね。
4.地図記号
3年生で学習する地図記号。大人でも混乱することの多い地図記号はしっかり整理して覚えましょう。地図記号を大きめに描き、色を使った四角で囲んだものの下にその記号が意味するものの名前を書く。という方法でノートを仕上げていました。
5.特産物
各都道府県の特産物。地方ごとにまとめてみたり、野菜が特産物の県をまとめてみたり工夫することができます。
6.県庁所在地
都道府県の名前と県庁所在地が違う県を調べて覚えていくことも役立ちます。都道府県や県庁所在地は漢字で書くことを求められると思いますので、難しい漢字は大きめに色マーカーで書いて目立たせ覚えるなんていう書き方もおすすめです。
7.おもしろい計算方法
19×19までの計算方法や倍数の判定方法など、知っておくと素早く計算ができるテクニックがいくつかあります。学校ではあまり教えてくれないおもしろい計算の仕組み。自学で学ぶといいと思いますよ。
おすすめポイント
「秘密の数当てマジック」「5秒で分かる!連続する10個秘密の足し算」「えっ!ホント?31×39もすぐできちゃう!」本で紹介されている項目をいくつかピックアップしただけでも楽しそうな本であることがわかると思います。真面目に使えるテクニックから話のネタになるおもしろいものまで、数の世界を楽しめるおすすめの1冊です。
8. 詩をかきうつす
お気に入りの詩や心に響いた詩を書き写すことも書写の勉強になります。心を込めて丁寧に書写し、最後にお気に入りのポイントや感想を書き加えるといいですね。
9.漢字の成り立ち
漢字の成り立ちも調べるとおもしろいですし、その漢字を覚える際にも役立ちます。我が家では下村式漢字の本を1~6年生まですべて取りそろえ、日々の漢字の学習含め活用しています。
10.算数を理論的に説明する
計算や筆算の仕方、公式などを学んでいくと「なぜこの方法で求められるのか?」という疑問を抱くこともあります。疑問を抱いて原理を知ると、理解も深まり公式をど忘れしてしまったときにも冷静に導き出すことができます。算数の「なぜ?」を理論的に説明しながら自学で理解を深めましょう。
11.料理
たまには料理も自学で使用しました。ミリリットルやグラムの勉強にもなりますし、実際に料理を作って手順をわかりやすく書くことは意外と頭を使います。できた料理を絵に描いたり、感想やおいしく作るポイントも書くといいですね。
12.祝日調べ
ハッピーマンデーが導入され、年によって祝日の日が変わってしまったりする影響もあるのか、意外といまの子どもは祝日をきちんと知りません。何月何日が何の祝日なのか、なぜその祝日がその日に設けられたのか調べてみるとおもしろいですよ。
13.日本古来の行事にまつわるもの調べ
七草やお節、節分の由来など、代々大切に受け継がれてきた日本古来の行事。なぜお正月飾りを飾るの?春の七草とは?なぜ冬至にゆずを入れるの?代々大事にされてきたものを未来に伝えていけるよう、教養として身につけてほしいと思います。お節のそれぞれの由来なんて、とてもおもしろいですよね。絵を描いて、矢印を引っ張り由来を書いていくとにぎやかで楽しい1ページが出来上ります。時期に合わせて取り入れてみてください。
14.新聞記事まとめ
身近な気になるニュースを取り上げ、その感想を書く少し高度な自学です。ネットニュースでも新聞でもいいですが、左のページに記事を貼り、右のページに題名と感想を書きます。なぜその記事を取り上げたのかを書き加えたり、記事の要約までできると立派ですね。時事問題に対してアンテナを張ること、少し難しい文章を読みとる力、要約や感想で自分の意見をまとめる力、など高学年になるにつれ磨いていくべき力がつきますので、かわいい動物が生まれたニュースでも台風のニュースでも、興味を持った些細な記事からで構いませんので、月に2回くらいは意識して取り組むといいと思います。
15. 学校の授業の復習
結局のところ、学校が一番取り組んでほしいと思っているのはこれだったりします。特に高学年になると、日常生じた疑問を調べたり、趣味にまつわることを掘り下げたりな自学が続くと「復習を優先しましょう」なんて書かれてしまうこともあります。復習もせっかく自学で取り組むのであれば工夫して、より効果的に行いましょう。
効果的な復習の取り組み方についてはこちらの記事をCheck!

まとめ
いかがでしたでしょうか。毎日となるとネタに困ってしまうこともあるかもしれませんが、ことわざひとつとっても、「体にまつわることわざ」「失敗に関連することわざ」など細分化してまとめていくと何度でも取り入れることができます。また、困ったときは復習を優先すれば間違いありません。取り組みやすい算数もそうですが、我が家では特に理科と社会は授業のあった日はその復習を優先するよう伝えていました。週のうち数回しかない理科や社会、はたまた家庭科などは、テストの前に慌ててしまうことも多いのではないでしょうか。授業の都度復習をしていけば記憶を呼び戻すのも容易になります。テストで慌てないように準備をするのも自学の大きな役割ですね。